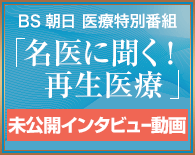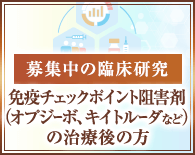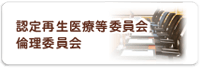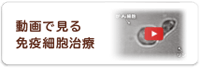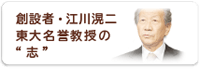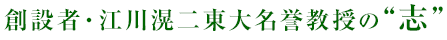 Vol.3 免疫細胞治療しかない
Vol.3 免疫細胞治療しかない
がん免疫学の研究者として、患者さんたちのために何ができるのか。

研究室にて
江川先生はご両親をがんで亡くされ、大学入学後はがんの研究に携わり、基礎研究で業績を重ねてきた教授です。研究の中でも、がんと免疫に関する世界的な研究の進展を目の当たりにし、自身でも、がんに対する免疫の働きについて手ごたえをつかんでいました。
治療の副作用から患者さんを救うには、副作用のない治療を開発するしかない、それには自分のがん免疫学の知識を活かせる免疫細胞治療しかない。
江川先生はそう決意し、それまでの基礎研究から患者さんの治療を念頭においた研究を開始したのです。
しかし、当時、免疫細胞治療は大学や公立のがんセンター等の研究で治療効果も示されていたものの、一方で医師たちからまったく信頼されない民間療法的なものが多く、理論的根拠も十分とは思えないものでした。
その時、江川先生の背中を後押ししたのは、科学者は先入観を持ってはいけないという信念だったのかもしれません。江川先生は、「私の研究者としての一生は、先入観を捨てることを目標にしてきたようにも思われます」(同書)とも述べています。
当時、まだまだ免疫細胞治療は発展途上でした。しかし、末期がんが治った人が少数でもいるならば、そこには何らかの理論的根拠があるはずだ。先入観を捨てて、そういった事例も観察し、研究を続けてみる必要がある。江川先生はそう考えるようになりました。
 CHINESE
CHINESE
 資料請求
資料請求