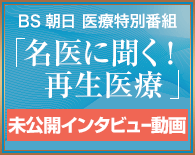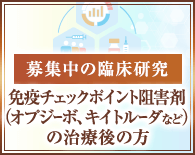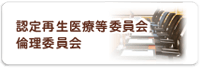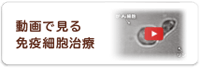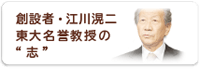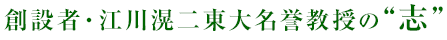 Vol.2 がん患者さんたちとの約束
Vol.2 がん患者さんたちとの約束
江川先生がそう思うようになったのには、いくつかの伏線があります。
その一つが、江川先生ご自身の病気でした。
江川先生は、教授になって数年後の50歳を過ぎたあるとき、ウイルス性心筋炎で3カ月間の入院を余儀なくされました。そこで、江川先生はある光景を目にします。
それは、同室の白血病患者たちが、抗がん剤治療の副作用に苦しむ様子でした。
驚くほど血色が悪く、これこそ病人…という状態で、具合が悪いといえども普通の生活をしていた江川先生は恥ずかしい思いをされたそうです。
白血病は、抗がん剤が有効とされているがんの一つです。医者である江川先生は、治療のためにはある程度の苦痛を我慢することも必要であると理解しており、また、抗がん剤を全面的に悪いと思っているわけでもありませんでした。
一方、治療の苦痛に耐え忍ぶ患者さんを目にすると、果たして、自分のがん研究はこの患者さんたちの役に立っているのであろうか…と自問自答するのでした。
そんな後ろめたさもあり、江川先生は自分ががんの研究者であることを同室の患者さんたちに明かせませんでしたが、時間が経つにつれ、それも周囲の知るところとなりました。すると、患者さんの何人もが
「苦しむがん患者を救う研究をぜひやってほしい」
と頼んできたのです。
これは衝撃でした。江川先生はその時の心境をこう述懐しています。
「『私にそんなことができるわけがない』と思いつつも、『わかりました』と、患者さんがたに約束する以外、どうすることもできませんでした」(同書)
 CHINESE
CHINESE
 資料請求
資料請求