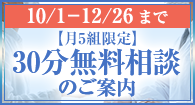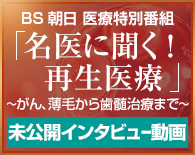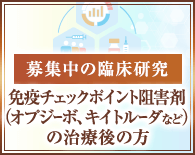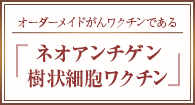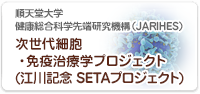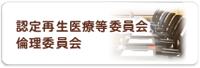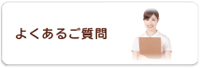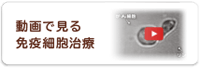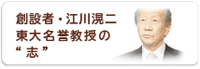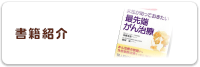仕事に従事されている方ががんになった場合、「治療後に職場復帰できるのだろうか」「復職までどれくらいかかるのか?」といった不安や疑問を感じるでしょう。
現代は医学の進歩により、がん治療から仕事復帰までにかかる期間は従来より短縮傾向にありますが、計画的な復職を目指すためにも、おおよその目安や必要な準備についてチェックしておくことをおすすめします。
本記事ではがん治療から仕事復帰までにかかる期間の目安や、復職までの具体的なステップと必要な準備について解説します。近年のがん治療やがんの再発予防についても説明しているのでぜひ参考にしてください。
免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)
について、
さらに詳細を知りたいと
お考えの方へ
当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。
- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の
特長 -
- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める
- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案
- 標準治療との併用や再発予防にも対応
- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視
ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。
専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。
無料

- 資料請求・お問合せ
 当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
詳しくはお電話やフォームからお申込みください。
- メールフォームはこちら
資料請求
がん治療から仕事復帰までにかかる期間の目安
がん治療から仕事復帰までにかかる日数はがんの症状や治療内容などによって異なりますが、内視鏡治療など全身への負荷が少ない治療であれば、数日~数週間の休職後に復職できる可能性が高いといわれています(※1)。
一方、手術療法や薬物療法、放射線療法など全身への負荷が大きい治療を行った場合は復職までにある程度の期間を要する可能性があります。ある研究によれば、がんで病気休暇を開始してから1年が経過するまでにフルタイムで復職した人の割合は62%、復職までに要した病休日数の中央値は201日です(※2)。
このように、がんの症状や治療法によっては復職までに半年以上の日数がかかることもあるため、治療計画や復職計画については医師とじっくり相談しつつ、勤め先とも話し合って進めていくことが大切です。
※参考:内閣人事院事務局総局.「国家公務員のがんの治療と仕事の両立支援ハンドブック」p5.
https://www.jinji.go.jp/content/000002602.pdf ,(参照2024-11-14).
※参考:厚生労働科学研究成果データベース.「がん患者の就労継続及び職場復帰に資する研究 令和元年度総括・分担研究報告書」p1.
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2019/201908012A.pdf ,(参照2024-11-14).
復職が難しくなる要因
がん治療からの復職が難しくなったり、長引いたりする要因は複数ありますが、大きな原因はがん治療による体力の低下や疲労感です。特に手術や薬物、放射線を用いた治療を行うと体に大きな負担がかかるため、体力が低下する傾向にあります。
こうした影響から、治療中はもちろん、治療後もがん関連疲労と呼ばれる慢性的な倦怠感やだるさに悩まされる患者さんは多く、がん患者さんを対象としたWeb調査では、中等度の疲労を感じる人が46.4%に上ったという結果が報告されています(※)。
慢性的な倦怠感やだるさは仕事に支障を来す原因になり得るため、治療後の復職までに長い日数を要する人も少なくないようです。
また疲労感や体力低下以外にも、頭痛や腰痛といった痛み、食欲低下、吐き気、便秘や下痢、集中力や判断力の低下などに悩まされている人もいます。さらに、不眠症やメンタルヘルスの不調によって仕事復帰がなかなか進まないケースも報告されています。
このように復職を妨げる要因は複数あり、かつ症状の度合いにも個人差があるので、無理にご自分を追い込まず、症状や体調に合わせた働き方を模索していきましょう。
※参考:厚生労働科学研究成果データベース.「がん患者の就労継続及び職場復帰に資する研究 令和元年度総括・分担研究報告書」p4.
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2019/201908012A.pdf ,(参照2024-11-14).
がん治療から仕事復帰する際のステップ
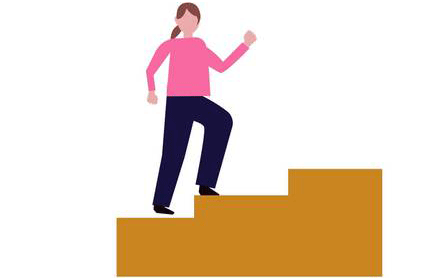
がん治療から仕事に復帰するまでにはいくつかのステップを踏む必要があります。焦って復職すると無理がたたって心身に不調を来す可能性があるので、段階的に進めることが大切です。
ここではがん治療から仕事復帰までの流れを次の5ステップに分けて説明します。
- 1.勤務先から勤務情報提供書を提出してもらう
- 2.意見書や診断書を作成してもらう
- 3.勤務先に復職申請書を提出する
- 4.復職までのプランについて話し合う
- 5.少しずつ仕事に復帰する
1. 勤務先から勤務情報提供書を提出してもらう
勤務情報提供書とは、患者さんの勤務先に関する情報を主治医に提供するための書類です(※)。主治医は勤務情報提供書を基に、がん治療後の患者さんが職場に復帰できるのか、またどのような仕事に従事できるのか等の判断を下すことになります。
勤務情報提供書の書式は任意ですが、一般的に以下のような項目を記載します。
- ●職種
- ●職務内容
- ●勤務形態
- ●勤務時間
- ●通勤方法・通勤時間
- ●休業可能期間
- ●有給休暇日数
- ●利用可能な制度
勤務情報提供書は勤務先の上司や管理職などに記載してもらうものなので、勤務先に連絡して作成を依頼しましょう。書類ができたら主治医に提出し、その内容を基に復職の時期や復帰までの計画について話し合います。
※参考:厚生労働省.「企業・医療機関連携マニュアル(解説編)」p4.
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000204439.pdf ,(参照2024-11-15).
2. 意見書や診断書を作成してもらう
勤務情報提供書や、患者さんとの話し合いの内容を基に、主治医に職場復帰に関する意見書や診断書を作成してもらいます。職場復帰に関する意見書には、以下のような項目が記載されます。
- 1.復職の可否とそれに対する意見
- 2.就業上の配慮の内容
- 3.面談実施日
- 4.記載内容の措置期間
2の「就業上の配慮の内容」には、例えば時間外勤務や出張、交替勤務は可能か否か、作業転換や配置転換、異動が必要かどうか、就業時間の短縮が必要か否かなどを記載します。なお、意見書を作成するのは主治医ですが、記載する内容には患者さんの希望や意見も反映されることも押さえておきましょう。
3. 勤務先に復職申請書を提出する
主治医が作成した意見書や診断書を添えて、勤務先に復職申請書(復職届)を提出します。復職申請書は会社ごとに書式が決まっているケースが多いので、勤務先まで取りに行くか、あるいは郵送してもらいましょう。
なお、復職申請書には、休職の傷病事由(がん)や、復職の事由、復職予定日などを記載します。
4. 復職までのプランについて話し合う
復職申請書を提出したら、後日、勤務先と職場復帰までのプランについて話し合う面談を行います。具体的には、勤務先に提出した書類を基に以下のような項目について決定・確認します。
- ●勤務形態
- ●勤務時間
- ●勤務内容
- ●復職後のサポート
- ●利用できる制度
一方、上司や産業医に対しては、現在の症状や今後の治療スケジュールに加え、通勤や業務に影響を及ぼす可能性のある副作用症状などを説明します。これらは医師が作成した意見書や診断書などにも記載されていますが、文字だけでは伝わらないことも多いので、口頭で丁寧に説明した方が良いでしょう。
また復職について不安なこと、や気がかりなことがあれば、些細なことでも尋ねておくことをおすすめします。不安要素を残したまま復職すると、心身に負担がかかって体調を崩す可能性があるため要注意です。
5. 少しずつ仕事に復帰する
勤務先と取り決めた復職日から、徐々に仕事へ復帰します。ただし、最初から頑張り過ぎると疲れてしまうので、しばらくの間は無理のない範囲で就労し、少しずつ心身を慣らしていきましょう。状況に応じて短時間勤務やフレックスタイム制、テレワークなどを利用すれば、心身への負担を軽減できます。
なお、復職前に決めたプランはあくまで暫定のものです。実際に復職してみて、「業務内容がきつい」「副作用がつらい」などと感じたら、遠慮せずに上司や産業医に相談しましょう。治療計画についても、症状や状態に応じて途中で変更する可能性があるため、復職後も適宜、勤務状況の調節は必要になります。
がん治療から仕事復帰のために必要な準備
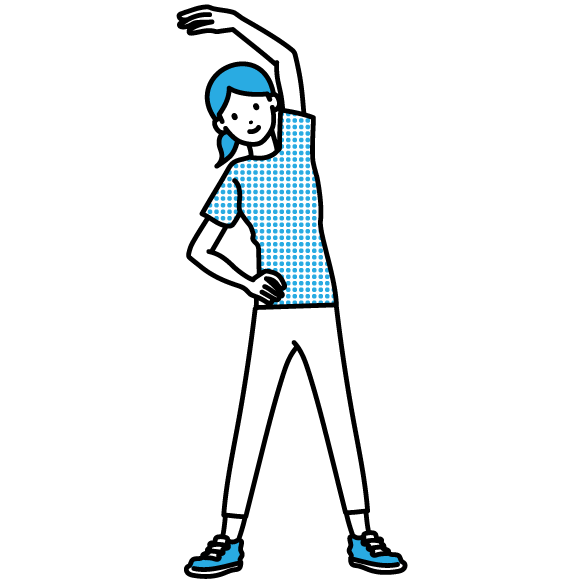
がん治療からなるべくスムーズに、かつ無理なく職場へ復帰するには、しっかり準備をしておくことが大切です。ここでは、復職に向けて準備すべきことやチェックすることを5つご紹介します。
- ●体力の回復に努める
- ●生活リズムを戻す
- ●通勤ルートの確認・見直し
- ●外見のケアを行う
- ●利用できる制度を調べる
体力の回復に努める
前述した通り、がん治療後は、治療による負荷や療養中の運動不足が重なり、体力が著しく低下する傾向にあります。そのままの状態では復職しても通勤や業務がつらくなる可能性があるため、復職手続きを進めつつ、運動などに取り組み体力を回復させましょう。
ただし、いきなり激しく体を動かすと体調を崩してしまう恐れがあるため、最初は日常生活の中でなるべく歩くことを心掛けるのがおすすめです。例えば、近所のスーパーやコンビニまで歩いてみる、家の近くを散歩する、などが挙げられます。
慣れてきたら少しずつ歩く時間を増やしたりや距離を伸ばしたりしていけば、徐々に治療前の体力へ近付けることができるでしょう。
生活リズムを戻す
入院中や休職している間は、働いていたときと比べて生活リズムが乱れがちです。特に起床時間がずれている場合は、出勤時間に合わせて目覚ましをセットするなど、復帰後と同じ生活リズムに戻すことを意識しましょう。
さらに、食事や就寝の時間も調整しておくと、復帰後の生活によりスムーズに移行しやすくなります。
通勤ルートの確認・見直し
がん治療後は、疲労感や体力の低下、薬の副作用などによる排せつ頻度の変化などで、体が思うように動かなくなりがちです。特に自宅から勤務先まで距離がある場合、徒歩通勤につらさを感じたり、交通機関で移動中にトイレに悩まされたりする可能性があります。
そのため、復職前に一度通勤ルートをたどって、問題なく出社・退社できるのか確認しておきましょう。もし途中で小休憩やトイレのための下車が必要だと感じたら、治療前よりも早く家を出て通勤時間にゆとりを持たせるなどの工夫を取り入れます。
また薬の副作用で通勤が困難と感じたら、投薬の種類や方法を見直せないのか主治医に相談するのも一つの方法です。
他には、万一の場合に備えてヘルプマークを身に付けておくのも有効でしょう。ヘルプマークとは、外見からは分かりにくい問題を抱えている方が、援助や配慮を必要としていることを周囲に報せる目的のマークです(※)。
がん治療後の疲労感や痛みなどは、事情を知らない人からすると判断が難しいです。そのような場合でもヘルプマークを付けていれば、公共交通機関で席を譲ってもらえたり、動作が困難なときに支援してもらえたりする確率が高くなります。
ヘルプマークは公共交通機関や病院などで無償配布されているため、自治体のWebページなどで情報を確認してみましょう。
※参考:東京都福祉局.「ヘルプマーク」.
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html ,(参照2024-11-15).
外見のケアを行う
抗がん剤治療を受けると、副作用として頭髪をはじめとする体毛が抜けることがあります。外見の変化が仕事に影響を与える可能性がある場合は、治療用のウィッグや付けまつげなどを用いて外見のケアをしてみましょう。
なお、ウィッグの種類は頭部全体をカバーするフルタイプ、一部の箇所のみをカバーする部分タイプに加え、帽子やバンダナなどの小物と組み合わせたタイプなどさまざまな種類があります。素材や形状、通気性、重量、価格帯なども製品ごとに異なるので、予算やニーズに合わせて選ぶのがおすすめです。
自治体によっては治療用ウィッグの購入費を助成する制度を設けている可能性があります。制度の有無や内容を知りたい方は、住所地のある市町村窓口やがん相談支援センターに問い合わせてみましょう。
利用できる制度を調べる
勤務先と復帰プランについて話し合うときにもチェックしますが、今一度復職後に使用できる制度を確認しておきましょう。例えば、フレックスタイムやテレワークを利用できるか、勤務軽減措置のルールはどうなっていのるか、復職に伴う慣らし出勤制度はあるのかなど、です。
また企業によっては半日単位、あるいは時間単位で有給休暇を取得できる制度を設けているところもあります。丸一日休むほどではなく、徐々に体を慣らしていきたいという場合に便利な制度なので、利用の可否について調べておくと良いでしょう。
がん治療やがんの再発予防について
がん治療は退院と同時に終了するわけではなく、根治や再発防止を目指して根気強く通院治療する必要があります。復職後の治療スケジュールは人によって異なりますが、外来での放射線療法や薬物療法、ホルモン療法などを行うのが一般的です。
また近年は従来のがん治療に加え、免疫療法に注目が集まっています。
免疫療法とは、人が本来持っている免疫の機能を応用してがんの治療や再発防止を目指す療法です。免疫療法は場所を限定せず、全身に広がった進行がんに適応します。その他にも、がん細胞のみを狙って攻撃するため副作用が少ないことなど、従来の療法にはないメリットがあることから、手術療法や放射線療法、薬物療法と並ぶ治療法として普及しています。
免疫療法には免疫細胞治療や免疫チェックポイント阻害剤など、さまざまな種類があるため、主治医と相談しながらご自身に適した治療法を探しましょう。
がん治療後の仕事復帰は焦らず、段階的に進めよう
がん治療後は、疲労感や体力の低下、薬の副作用などによって通勤や業務に支障を来すことがあります。そのため、復職については主治医や勤務先と相談しながら、無理をせずマイペースに進めていくことが大切です。もし仕事に復帰した後も再発予防をはじめとする通院治療を検討する場合は、ご自分の症状やニーズに合った治療法を選びましょう。
瀬田クリニック東京では、全身のがんに有効で、かつ副作用の少ないがん免疫療法を行っている専門医療機関です。オーダーメードの個別化医療により、一人ひとりに合った治療を提案いたします。復職後のがん治療にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
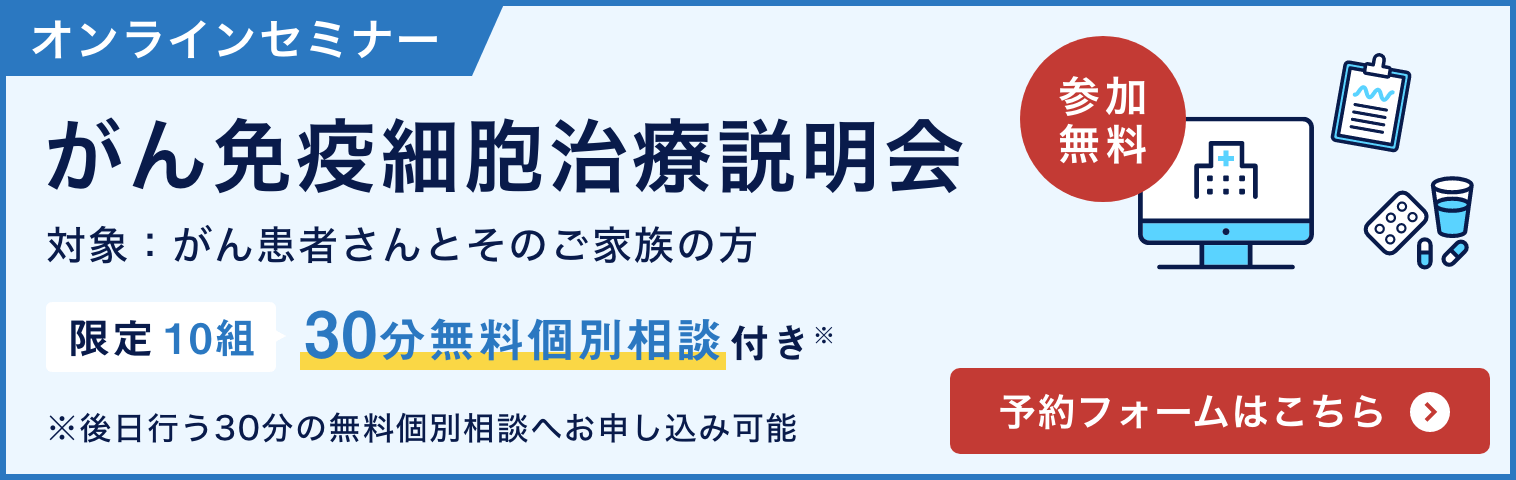
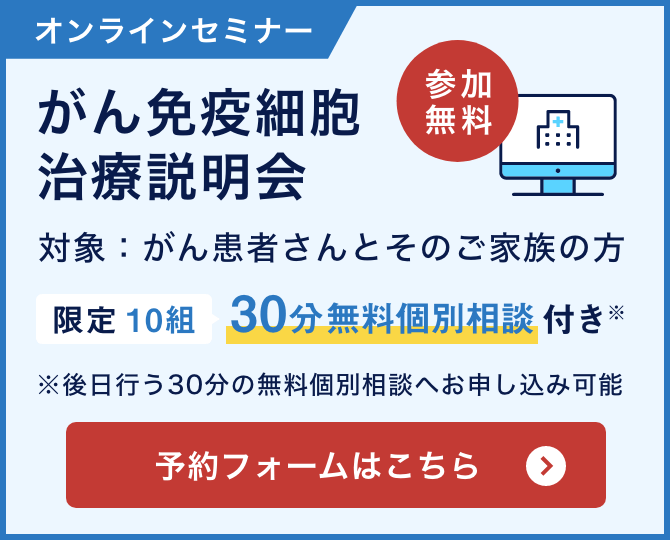
無料

- 資料請求・お問合せ
 当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
詳しくはお電話やフォームからお申込みください。
- メールフォームはこちら
資料請求
関連性の高いコラム記事
-

ストレスは悪性リンパ腫の原因になる?リスク要因や免疫との関係も含めて解説
2025.11.14瀬田クリニック東京
-
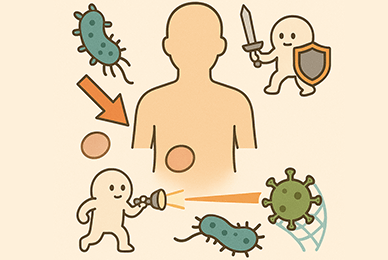
免疫力の高い人の特徴は?免疫力アップの方法を解説
2025.06.20瀬田クリニック東京
-
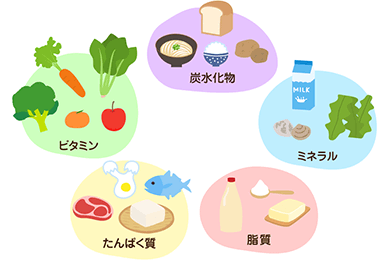
がん細胞が嫌う食べ物・生活習慣とは?がんに対応するための具体的なポイントを解説
2025.06.06瀬田クリニック東京
-

がん治療後、仕事に復帰するために必要な手続きや準備を分かりやすく解説
2025.04.11瀬田クリニック東京
-

がん再発への不安が消えない場合はどうする?不安から生じる症状や不安
2025.03.21瀬田クリニック東京
-

親ががんになって仕事が手につかないときはどうする?親のがんとの向き合い方と自身のケアの仕方を解説
2025.03.07瀬田クリニック東京
-
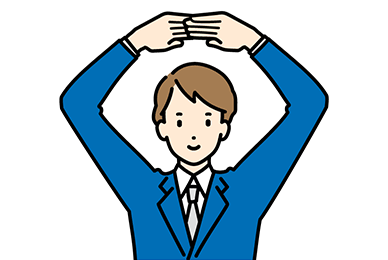
がん治療中でも働ける仕事とは?仕事を続けるメリット・デメリットや働きやすい環境を紹介
2025.02.28瀬田クリニック東京
-

がんになっても運動は重要?がん予防と運動の関係や効果、具体的な方法を解説
2025.01.31瀬田クリニック東京
-
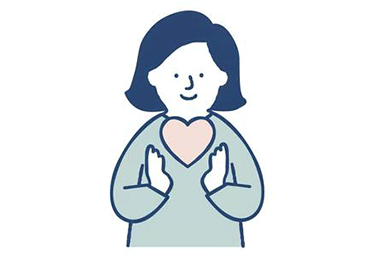
がん患者さんに多い精神症状とは?がんと診断されたときの心の変化やストレスへの対処法を紹介
2025.01.17瀬田クリニック東京
-

がんを怖いと感じる理由とは?がんに対する恐怖心や不安との向き合い方
2024.12.20瀬田クリニック東京
-

がん治療中の食事とは?副作用が出た時の食事や食事療法の注意点を解説
2024.11.1瀬田クリニック東京
 CHINESE
CHINESE
 無料説明会
無料説明会 資料請求
資料請求