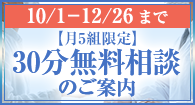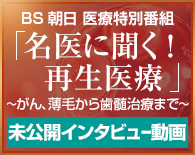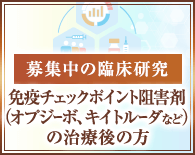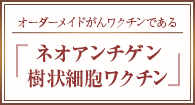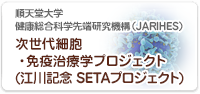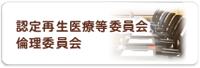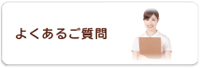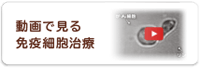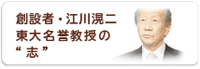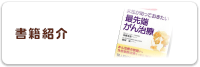運動が制限される病気もありますが、がんの場合は体力作りや合併症の予防など、むしろ運動を行うことでさまざまな効果が期待できます。また、運動はそれ自体にがんの予防効果があるため、習慣化するのがおすすめです。
本記事では、がんと運動に関する研究データを紹介した後、がん患者さんにとって運動が重要な理由と効果、具体的な運動方法を紹介します。
免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)
について、
さらに詳細を知りたいと
お考えの方へ
当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。
- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の
特長 -
- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める
- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案
- 標準治療との併用や再発予防にも対応
- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視
ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。
専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。
無料

- 資料請求・お問合せ
 当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
詳しくはお電話やフォームからお申込みください。
- メールフォームはこちら
資料請求
がんと運動に関する研究データ
さまざまな研究から、定期的な運動の継続には死亡リスクの低下や病気の予防、不安症状の軽減、幸福感の向上など多くの効果があるとされています(※)。
さらに運動には、がんの予防効果も認められているため、日頃から適度な運動を行うことが大切です。研究データを基に紹介します。
※参考:厚生労働省.「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(案)」p3.
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001171393.pdf ,(参照2024-10-24).
がんの予防方法には"運動"が含まれる
化学的根拠に基づいたがんの予防指針には、公益財団法人がん研究振興財団の「がんを防ぐための新12か条」や、国立研究開発法人国立がん研究センターの「日本人のためのがん予防法(5+1)」などがあります。
上記のどちらにも共通している項目には、禁煙、節酒、食生活の見直し、適正体重の維持、定期的な運動があります。なかでも、体を動かすことは他の予防方法と同じくらい重要です。実際に、身体活動量の多い人は少ない人と比べ特定のがんに罹患するリスクを10%以上下げる可能性があるとの発表があります(※)。
※参考:※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト.「身体活動量とがん罹患との関連について」.
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/322.html ,(参照2024-10-24).
がん予防のために科学的に推奨される運動内容
厚生労働省は、悪性腫瘍(がん)を含むさまざまな病気の予防に効果のある運動量の指針を公表しています。なお、ガイドラインは2024年1月に改訂版が発表されているため、ここでは従来版・改訂版どちらも紹介します。
「健康づくりのための身体活動基準2013」の運動内容
2013年に発表された「健康づくりのための身体活動基準2013」では、年齢別に以下のような活動を推奨しています(※)。
| 身体活動(生活活動+運動) | 運動 |
|---|---|
| 強度(負担やきつさ)を問わず身体活動を毎日40分 | - |
| 身体活動(生活活動+運動) | 運動 |
|---|---|
| 歩行か歩行と同程度の身体活動を毎日60分 | 息が弾み汗をかく程度の運動を毎週60分 |
※上記に加え体力維持として、性・年代別に設定された強度の運動を3分以上継続します。詳しい内容は「健康づくりのための身体活動基準2013」のを参照してください。
生活活動とは家事や仕事など、日常生活に伴う活動です。なお、上記の運動量に達さないと、がん予防の効果が得られないわけではありません。
全体の方向性としては、今より少しでも身体活動を増やしたり、運動習慣を持つようにしたりすることが示されました。
※参考:厚生労働省.「運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書 」p8,12.
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple-att/2r9852000002xpqt.pdf ,(参照2024-10-24).
「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」の運動内容
「健康づくりのための身体活動基準2013」を改訂した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」では、年齢区分を廃止し、運動に筋力トレーニングを追加しました(※)。
| 身体活動(生活活動+運動) | 運動 |
|---|---|
| 歩行か歩行と同程度の身体活動を1日40分以上(1日約4,000歩以上) |
|
| 身体活動(生活活動+運動) | 運動 |
|---|---|
| 歩行か歩行と同程度の身体活動を1日60分以上(1日約8,000歩以上) |
|
また、上記に「座位行動」が新たに追加され、全体を通して長時間座りっぱなしの体勢を避けるように促しています。
全体の方向性としては、個人差を踏まえて量や強度などを調整し可能なものから取り組むこと、また今よりも少しでも多く体を動かすことが示されました。
今回、新たに筋力トレーニングが追加された根拠として、筋力トレーニングを実施した群は実施していない群と比べ、総死亡、心血管疾患、全がん、糖尿病、肺がんの発症リスクが10~17%低いと示されたことが挙げられます(※)。この効果は、有酸素運動の量に関わりません。さらに、筋トレは実施時間がわずかであっても上記の効果が得られると報告されています。
※参考:厚生労働省.「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」p9,19.
https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf ,(参照2024-10-24).
運動ががんを予防するメカニズム
「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、大腸がんや子宮体がん、乳がんなどの一部のがんは身体活動により予防や改善が期待できるとしています(※)。理由として、運動により免疫機能の改善などが起こり、腫瘍の成長が抑制するのではないかと考えられています。
なお、運動ががんを予防する効果は多くの研究で示されているものの、具体的なメカニズムの大部分はまだ解明されていません。
※参考:厚生労働省.「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」p32.
https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf ,(参照2024-10-24).
がん治療期間中の運動とがん治療後の運動

運動はがんの予防だけでなく、すでにがんに罹患している患者さんや治療後の患者さんにも、さまざまな効果が期待できます。
がん治療期間中の運動の効果
がんの治療期間中の運動により得られる効果は以下があります。
- ●治療に伴う身体機能の低下を防ぐ
- ●手術に伴う合併症などを予防する
- ●寝たきりを防いでがんの治療を継続できる
- ●精神的ストレスが緩和する
- ●リハビリの自信になる
がんの治療では機能障害や体力の低下が起こるため、これを防止する上でも運動は大切です。
がん治療後の運動の効果
がん治療後の運動により得られる効果は以下の通りです。
- ●治療後に低下した体力を改善する
- ●生活の質を高める
- ●がんの再発を防止する
がんの治療後は体力や身体機能が大きく低下しています。日常生活を取り戻すためにも運動は大切です。また、運動はがんの予防効果もあるため、がん治療後であっても再発防止効果が期待できると考えられます。
がん患者さんが運動する際の注意点
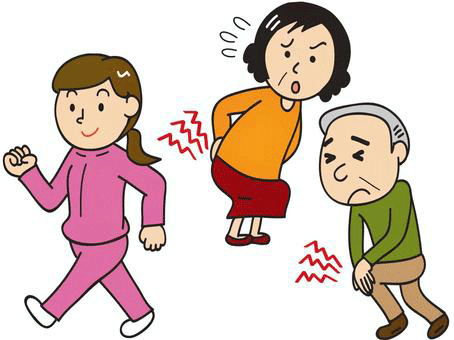
がん患者さんが運動する際は、事前に主治医と相談し、運動をしても問題がないか確認しましょう。体調が悪いときは控え、また無理に運動量を増やさないことも大切です。運動習慣が身に付いた後も、定期的に医師に状況を伝えましょう。
運動を開始する前に主治医に相談する
事前に主治医に運動をして良いか確認してから開始しましょう。運動はがんの改善や予防効果が期待できるとはいえ、患者さんの状態によっては適さない可能性があります。「運動をしても良いか」ではなく、どのような種類・強度の運動を、どの程度して良いのか、具体的に確認するようにしましょう。
体調が悪いときは運動を控える
運動は体調が良いときに実施しましょう。特に38度以上の発熱やめまい、動悸、体に痛みがあるときは無理に行ってはなりません。
ただし、場合によっては痛みを伴っても運動を実施しなければならないこともあります。例えば乳がんの手術では、術後に痛みが残っていてもリハビリが必要です。
体調不良の症状が運動を控えた方が良いものか、それとも運動により回復するものなのか判断がつかないときは、主治医に相談して確認しましょう。
一気に運動量を上げない
運動量は徐々に上げて体に適応させましょう。がん患者さんの活動量は治療中であれば治療前と比べ10%程度、治療後であれば以前と比べ30%程度低下するとされています(※)。
そのため、例えばがんに罹患する前は水泳が趣味だった人が、体調が良いからといって以前と同じ距離を一気に泳ごうとすれば、体に大きな負担がかかります。運動量は無理のない範囲で少しずつ、様子を見ながら増やしていきましょう。
※参考:社会医療法人愛仁会千船病院.「がんの運動療法(がんリハビリ)|リハビリテーション科」.
https://www.chibune-hsp.jp/chibune_now/exercise_-is_important_for_cancer/ ,(参照2024-10-24).
運動を開始した後も定期的に主治医に確認する
運動を開始した後も、定期的に主治医に状況を説明し、指示を仰ぐようにしましょう。特に、リハビリではやり方を間違えると効果が出ないばかりか、逆効果になってしまうケースも考えられます。日頃どのような運動をどの程度行っているか、記録をしておくと確認しやすいでしょう。
運動と免疫療法の併用
がんの治療では、さまざまな理由から各療法と運動療法の併用が行われます。例えば、手術療法と併用するのは合併症や後遺症の予防、術後のスムーズな回復が目的です。また、化学療法や放射線治療では、体力・筋力の低下や倦怠感の軽減に役立てるために併用されます。
さらに運動療法は、治療方法の一つである免疫療法とも併用が可能です。運動には免疫機能を強化する働きがあるため、免疫療法との相乗効果が期待できます。
免疫療法は免疫が持つ機能を応用してがんを治療する方法
がんの免疫療法とは、自分の体が持つ免疫機能を応用し、がんを治療する方法のことです。
免疫には、異物を認識し体から排除する働きがあります。免疫が十分に機能していれば、病気に罹りにくくなるだけでなく、罹っても抵抗することが可能です。
免疫療法は1970年代から注目され始め、現在では以下のようにさまざまな方法があります。
- ●免疫チェックポイント阻害剤
- ●免疫細胞治療
- ●がんワクチン
- ●抗体医薬
- ●サイトカイン療法
- ●免疫賦活剤など
がんの三大治療法には手術療法・放射線療法・薬物療法(化学療法)があり、免疫療法は「第4の治療方法」として注目されています。免疫療法の種類について詳しく知りたい方は「免疫療法の種類」をご覧ください。
免疫療法のメリット
免疫療法のメリットは以下の通りです。
- ●副作用が少ない
- ●全身に広がったがんにも適用できる
- ●効果が表れれば長期間持続する
免疫療法の中でも自らの免疫を使って治療をする「免疫細胞治療」は、副作用が少ない点がメリットです。もともと自分の持っている細胞を使うので、抗がん剤のように正常な細胞を傷つけることがありません。体力が低下しにくく、生活の質を維持しながらがん治療を進められます。
また、免疫細胞治療は全身に作用する治療方法のため、初期のがんから転移したがんまで治療が可能です。一部の血液系のがんを除いたほとんどのがんに対応でき、進行がん・再発がんを問わず治療を検討できます。
効果が表れるまで時間がかかるものの、現れた後は持続期間が長い点も特徴です。このため、がんの再発予防効果も期待できます。
免疫細胞治療の症例紹介
症例
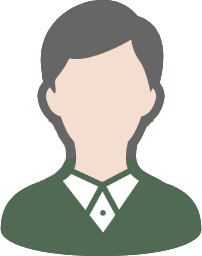 59歳 男性
標準治療に抵抗性の肺への転移がある進行肝細胞がん(Ⅳ期)に対して、免疫細胞治療単独治療で、著効した一例
59歳 男性
標準治療に抵抗性の肺への転移がある進行肝細胞がん(Ⅳ期)に対して、免疫細胞治療単独治療で、著効した一例
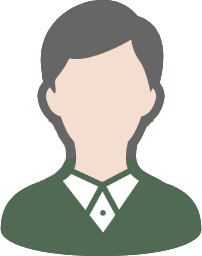 59歳 男性
59歳 男性治療までの経緯
2004年6月に肝細胞がんと診断され、TAE(肝動脈塞栓療法)と抗がん剤(エピルビシン)を実施したが無効であり、その後、肺転移も発見されたため、同年8月に抗がん剤(UFT)の内服治療を開始しました。しかしながら、腫瘍マーカーの急激な上昇と副作用(肝機能の悪化)のために断念し、同年9月より免疫細胞治療を開始しました。
症例
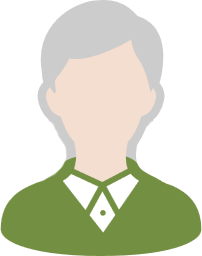 77歳 男性
Ⅳ期食道がんで標準治療終了後に免疫細胞治療を実施し肺転移が縮小し、さらに低用量のニボルマブ(オプジーボ)の併用により寛解、安定を得られている症例
77歳 男性
Ⅳ期食道がんで標準治療終了後に免疫細胞治療を実施し肺転移が縮小し、さらに低用量のニボルマブ(オプジーボ)の併用により寛解、安定を得られている症例
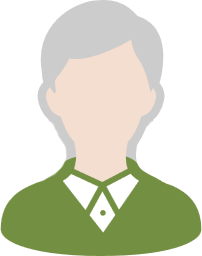 77歳 男性
77歳 男性治療までの経緯
2017年7月、物が飲み込みにくくなり検査を受けたところ、食道がんが発見され、既に多発性にリンパ節に転移していました。ステージⅣの診断です。
一旦、放射線化学療法が効果を発揮したものの、その後肺に転移。その後標準治療を続けましたが、転移巣が増大し2018年8月を最後に化学療法は中止。主治医と相談したところ、これ以上の標準治療はないとのことで当院を紹介されました。
運動はがん患者さんにもさまざまなメリットがある!

運動はがんの予防だけでなく、がん治療中には体力維持やストレスの緩和、治療後ではがんの再発予防など、さまざまな効果があります。そのため、短時間でも良いので、まずは運動する習慣を付けることが大切です。
免疫療法の専門医療機関 瀬田クリニック東京では、運動とも併用しやすい「個別化がん免疫細胞治療」を行っています。副作用を抑えたい、生活の質を維持したままがん治療を行いたいとお考えの方は、ぜひ以下をご確認の上、電話またはWebからお気軽にお問い合わせください。
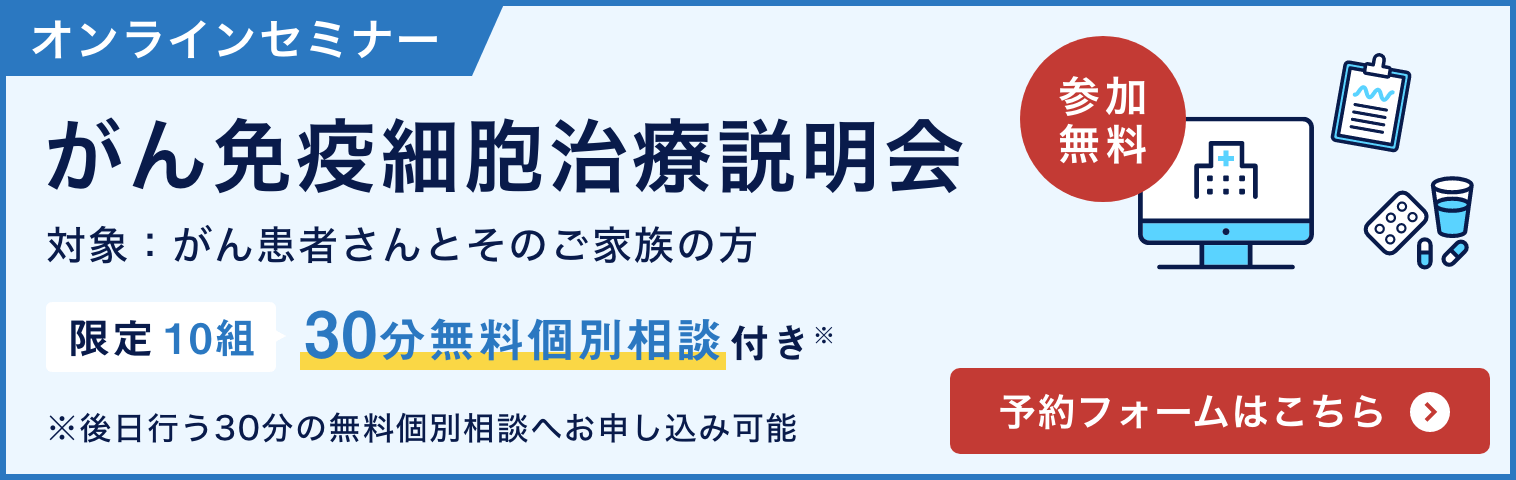
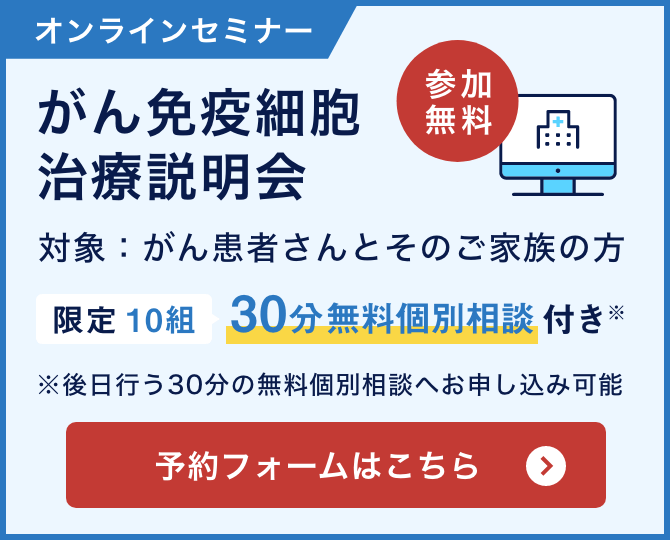
無料

- 資料請求・お問合せ
 当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
詳しくはお電話やフォームからお申込みください。
- メールフォームはこちら
資料請求
関連性の高いコラム記事
-

ストレスは悪性リンパ腫の原因になる?リスク要因や免疫との関係も含めて解説
2025.11.14瀬田クリニック東京
-
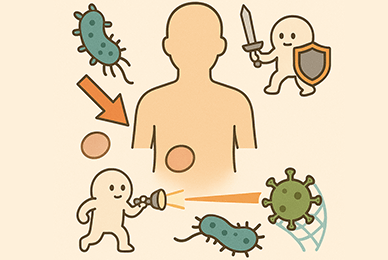
免疫力の高い人の特徴は?免疫力アップの方法を解説
2025.06.20瀬田クリニック東京
-
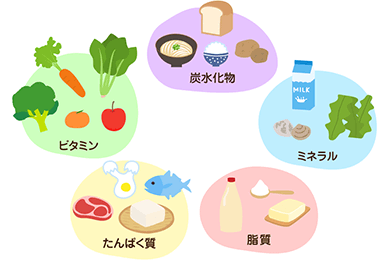
がん細胞が嫌う食べ物・生活習慣とは?がんに対応するための具体的なポイントを解説
2025.06.06瀬田クリニック東京
-

がん治療後、仕事に復帰するために必要な手続きや準備を分かりやすく解説
2025.04.11瀬田クリニック東京
-

がん再発への不安が消えない場合はどうする?不安から生じる症状や不安
2025.03.21瀬田クリニック東京
-

親ががんになって仕事が手につかないときはどうする?親のがんとの向き合い方と自身のケアの仕方を解説
2025.03.07瀬田クリニック東京
-
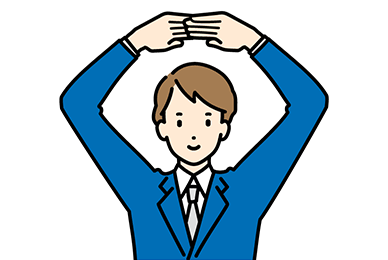
がん治療中でも働ける仕事とは?仕事を続けるメリット・デメリットや働きやすい環境を紹介
2025.02.28瀬田クリニック東京
-

がんになっても運動は重要?がん予防と運動の関係や効果、具体的な方法を解説
2025.01.31瀬田クリニック東京
-
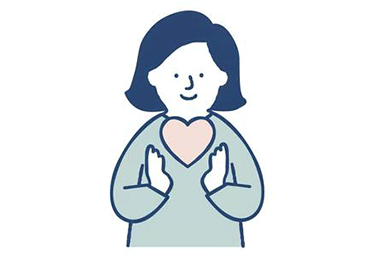
がん患者さんに多い精神症状とは?がんと診断されたときの心の変化やストレスへの対処法を紹介
2025.01.17瀬田クリニック東京
-

がんを怖いと感じる理由とは?がんに対する恐怖心や不安との向き合い方
2024.12.20瀬田クリニック東京
-

がん治療中の食事とは?副作用が出た時の食事や食事療法の注意点を解説
2024.11.1瀬田クリニック東京
 CHINESE
CHINESE
 無料説明会
無料説明会 資料請求
資料請求