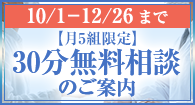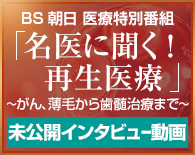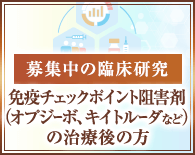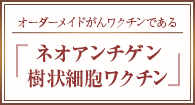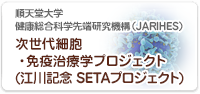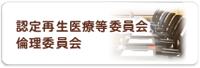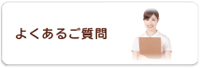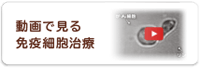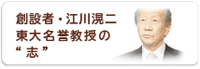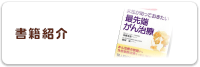がんは再発リスクが高い疾患とされており、例えば大腸がん治癒切除後の再発率は、ステージⅠで5.7%、ステージⅡで15.0%、ステージⅢで31.8%、全体で18.7%に及んでいます(※)。再発したケースの9割以上は術後5年以内であるため、患者さんは治療から少なくとも5年間は再発の不安を抱えることになります(※)。
中には再発の不安から心の病に罹ってしまう方もいるため、がん再発への不安が消えない方は、上手に向き合っていく方法を模索する必要があります。
本記事ではがん再発の不安から起こる症状や、不安との向き合い方、再発予防のために行えることについて解説します。
※参考:大腸癌研究会.「大腸癌治療ガイドライン医師用2022年版」.
https://www.jsccr.jp/guideline/2022/document.html ,(参照2024-11-20).
免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)
について、
さらに詳細を知りたいと
お考えの方へ
当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。
- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の
特長 -
- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める
- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案
- 標準治療との併用や再発予防にも対応
- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視
ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。
専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。
無料

- 資料請求・お問合せ
 当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
詳しくはお電話やフォームからお申込みください。
- メールフォームはこちら
資料請求
がん再発の不安から起こりがちな症状

「がんが再発するかもしれない」という不安が消えないまま過ごしていると、心身に不調を来しやすくなります。どのような症状が起こるのかは個人差がありますが、ここでは主な症状を5つご紹介します。
適応障害
適応障害とは、何らかのストレスが原因となって心身のバランスが乱れ、社会生活に支障を来している状態です。がんが再発するかもしれない、という不安は患者さんにとって非常につらいもので、時として日常生活が困難になるほど抑うつ状態になったり、強い焦りや緊張などを抱えたりします。また情緒面の変化が、飲酒や暴食、無謀運転、けんかといった行動に現れるケースも少なくありません。
適応障害はストレスに起因したものなので、ストレスの元が解消されれば自然と治まります。しかし、がん再発リスクをゼロにすることはできないため、不安やストレスとうまく付き合う方法を模索する必要があります。
うつ病
うつ病とは、気分の落ち込みや食欲低下、不眠、慢性疲労などの心身症状を伴う気分障害の一種です。発症の原因やメカニズムに関しては分からない部分が多いものの、精神的・身体的ストレスが一因になっているという説もあります。
うつ病になると、前述した症状の他、自分を責め続ける、涙もろくなる、反応が遅い、飲酒量が増えるといった行動が見られる上、頭痛や肩こり、動悸、胃部不快感、めまいなどの身体症状が現れることもあります。
うつ病の治療法には、抗うつ薬の投与による薬物療法や、認知行動療法などを軸にした精神療法等がありますが、何よりもまず、心身共にしっかり休養を取ることが重要です。
不安症
不安症とは、目の前の出来事や将来に対する過度な恐怖や不安により、社会生活や行動に何らかの影響を与える状態が6カ月以上(子どもの場合は4週間以上)続くことです。
不安症にはさまざまな種類がありますが、中でもがんの再発に不安を感じる方は以下の症状が出ることがあります。
- ●パニック障害
- ●全般性不安障害
- ●心的外傷後ストレス障害(PTSD)
パニック障害とは、突然理由のない激しい不安に襲われ、動悸やめまい、呼吸困難といった症状が起こる障害です。
症状は10分以内にピークに達し、その後は徐々に治まっていきますが、一度発症すると「また発作が起きたらどうしよう」という強い不安から、日常生活や社会生活が困難になる場合があります。原因ははっきり分かっていませんが、前述したうつ病などの発症に伴って起こることもあるようです。
全般性不安障害とは、生活上のさまざまなことが気になって極度の不安を感じる状態です。
一度がんに罹った方の場合、再発への不安や恐怖が引き金になり、小さなことにも過剰に不安を感じるようになります。そのため、日常生活でも常に落ち着かず、一日中そわそわしたり、過度なストレスから来る疲労やイライラが慢性化したりします。
心的外傷後ストレス障害(PTSD)は、死の危険に直面した後、自分の意思とは関係なくそのときの記憶がフラッシュバックし、不安や緊張が高まる状態のことです。がんになった人はつらい症状や治療を経験しているため、「再発したら再びつらい思いをするのでは」という恐怖心から、PTSDを発症するケースもあるようです。
いずれの症状も、抗うつ薬や抗不安薬の投与、精神療法などが主な治療法となります。
不眠症
不眠症とは、寝付きが悪い、眠りが浅い、早朝に目覚めて二度寝できないなど、睡眠に関するさまざまな問題を抱えた状態です。不眠症になると、睡眠不足に伴う倦怠感の他、食欲が減退したり意欲や集中力が低下したりと不調が出るため、日常生活や社会生活に影響を及ぼす恐れがあります(※)。
不眠症はストレスや疾患、薬の副作用などが主な原因であるため、がん再発への不安から不眠症に陥る患者さんは少なくありません。
また「眠りたいのに眠れない」というイライラがストレスを増長させる原因にもなり、放っておくと悪循環に陥ることもあります。不眠症を解消するには、ストレスの元をなくす他、就寝リズムの見直しや適度な運動などが有効とされています。
※参考:参考:厚生労働省.「不眠症」.
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-001.html ,(参照2024-11-20).
頭痛や吐き気、食欲不振などの身体症状
がん再発への不安が強くなると、ストレスから頭痛や吐き気、食欲不振など、体にも何らかの症状が現れることがあります。
また前述した障害の症状として、体の不調が起こることも少なくありません。精神的な障害から来る体の不調は、大元の原因となる不安や緊張などが解消されない限り改善は困難なため、がん再発の不安と向き合うことが大切です。
がん再発の不安との向き合い方
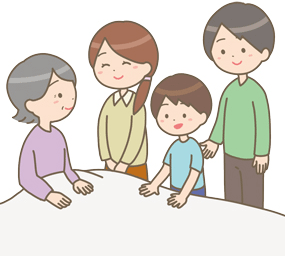
がんが再発するかもしれないという不安を抱え続けると、心身に大きな負担がかかり仕事や日常生活にまで影響を及ぼす恐れがあります。がん再発への不安をゼロにするのは難しいかもしれませんが、日常生活に支障を来さないよう、不安と向き合っていく方法を模索してみましょう。
ここではがん再発の不安との向き合い方を6つのポイントに分けて紹介します。
自分の不安・悲しみ、怒りなどの感情は自然な反応と理解する
患者さんの中には、強い不安や悲しみ、怒りなどを感じることそのものにストレスや失望を覚える方もいます。がんの再発リスクを完全になくすことができない以上、強い不安や動揺、緊張を感じるのは無理のないことです。
「がんと診断されていないのに不安になるなんて」「もっと強い気持ちを持たなければ」と自分を追い込んでしまうと、より強いストレスを抱えてしまう可能性もあります。
がん再発について不安や悲しみ、怒りなどの感情を抱くのは自然な反応だと理解し、ご自身の気持ちを否定しないことから始めてみましょう。
がん再発について正しい情報・知識を得る
がん再発に対して強い不安を感じている方は、無意識にがんや再発に関する知識・情報から目をそらしてしまいがちです。しかし、漠然とした不安や恐怖はかえって解消しにくく、いつまでたっても問題を解決できません。
なぜ不安なのか、どのようなことに恐怖を感じているのか、などを明確にした上で、がんや再発に関する正しい情報・知識が得られれば、不安感や恐怖感を和らげられる可能性があります。
がんや再発の情報・知識は本やインターネットなどから入手することもできますが、再発リスクはがんの種類や患者さんの病態などによって異なります。そのため、がん再発について不安や恐怖を覚えているのなら、まず患者さんの状態や経過を熟知している主治医に相談してみましょう。
心身の不調を感じたら主治医に相談する
がんの再発への不安が消えない人は神経過敏になっているケースが多く、発熱や頭痛、腹痛などの不調が起こると「再発の前兆ではないか」と怯える方も少なくありません。
例え原因が疲労や風邪だったとしても、明確な原因が分かるまでは不安や緊張が続く恐れがあります。こうした不安が頻繁に起こる場合は、心身の不調を感じた段階で主治医に相談しましょう。専門家に診察してもらった上で、体調の変化についてきちんと説明してもらえれば、漠然とした不安や緊張を緩和できます。
「こんなことで診察、相談してもいいのだろうか」と悩んでしまうかもしれませんが、不安やストレスを長く抱え込むと精神障害などを起こす原因にもなるので、思い切って相談することをおすすめします。
不安から気をそらす方法を探す
がん再発への不安が心の中の大部分を占めていると、いつ、何をしていてもストレスや緊張を感じてしまいがちです。そんなときは、不安から気をそらす方法を考えてみましょう。例えば、散歩や運動をして体を動かす、好きな音楽を聴く、ショッピングを楽しむなどが挙げられます。
ご自分が興味・関心を持っているものほどリラックス効果が高く、かつ集中しやすいので、がん再発への不安から気をそらしやすくなります。また自分なりの対処法を知っておけば、ふとしたときに再発への不安や恐怖を感じたときでも心を落ち着けやすくなるでしょう。
体や心のこわばりを解く手段として、腹式呼吸をマスターしておくのも一つの方法です。腹式呼吸には緊張でこわばった体や心を解きほぐす作用があり、ストレスのセルフケア方法として知られています。
腹式呼吸の方法は以下の通りです。
- 1.背筋を伸ばし、鼻からゆっくり息を吸い込む
- 2.お腹をへこませながら、口からゆっくり息を吐き出す
息を吐くときは、吸うときの倍の時間をかけることを意識するのがポイントです。
腹式呼吸は場所を選ばずに行えるため、仕事中などで他の方法が使えない場合に重宝するでしょう。
習慣化したい場合は、1日5回からスタートし、徐々に回数を増やして10~20回ほど行うようにするのがおすすめです。
身近な人や専門家に気持ちを打ち明ける
心の中にある不安や悩みを一人で抱え込もうとすると、かえってストレスがたまったり、不安が増長したりする原因となります。「誰も分かってくれない」「話しても仕方がない」などと悲観することなく、家族や信頼できる友人など、身近にいる人に気持ちを打ち明けてみましょう。
誰かに話すことで、自身がどのようなことに不安を感じているのか、何に対して恐怖を感じているのかを整理でき、問題解決につながることもあります。
身近な人には話しづらいという場合は、がん相談支援センターを利用するのもおすすめです。
がん相談支援センターとは、全国にあるがんに関する相談窓口のことで、患者さん本人はもちろん、家族の方も無料で相談できます。相談には看護師やソーシャルワーカー、心理士などが対応するため、専門家の視点から適切な支援やアドバイスを受けられます。
対面相談だけでなく、電話での相談や匿名相談も受け付けているので、がん再発に対する不安や悩みを誰かに話したいと思ったらがん相談支援センターの利用を検討してみましょう。
再発防止のための療法を受ける
がん再発への不安が強い場合は、再発防止のための療法を受けてリスク軽減に努める方法も有効です。がんの治療後、再発防止のために受ける療法を術後補助療法といい、主な方法として薬物療法や放射線療法、免疫療法などが挙げられます。
薬物療法は手術で除去し切れなかった微小ながんを死滅させるのに有用な方法です。全身に作用するため転移・再発防止に適しているものの、正常な細胞にも攻撃してしまうので、副作用のリスクが懸念されます。
放射線療法はがんに対して放射線を照射して攻撃する方法です。正常な細胞よりがん細胞に強い効き目を発揮するので、再発防止に効果的です。ただし、正常な細胞にダメージを与えることもあるため、副作用のリスクはゼロではありません。
また放射線は原則として、同じ場所への照射はできないことにも注意が必要です。
免疫療法は患者さん自身の免疫の力を利用してがんを攻撃する療法です。免疫療法には免疫チェックポイント阻害薬を使用する方法や、患者さんの免疫細胞を採取し、その力を活性化させてから体内に戻す方法など複数の種類があります。
いずれも患者さんの免疫の力を利用する点は共通しており、薬物療法や放射線療法よりも副作用のリスクが少ないところが大きな利点です。
ただし、どの免疫療法が効くのかは個人差があるため、適切な治療法を選択する必要があります。
がんの再発と向き合う際には、治療方針や選択肢を冷静に整理することが大切です。
当院では、再発がんの方に対しても免疫細胞治療をはじめとする個別化医療をご提案しています。
治療の流れや特徴については、こちらのページで詳しくご紹介しています。
がん再発の不安が消えないときはセルフケアを心掛けよう
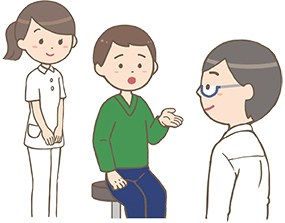
がん再発への不安を抱えたまま過ごしていると、心身に不調を来したり、日常生活に影響を及ぼしたりする原因になります。場合によっては適応障害や不安症などの症状が出ることもあるので、がん再発への不安が消えない方は、がんについて正しい情報・知識を得たり、身近な人に気持ちを打ち明けたりしてセルフケアに努めましょう。
また再発防止のための療法を受け、再発リスクを軽減するのも有効な方法の一つです。
瀬田クリニック東京では、患者さんの免疫細胞を採取し、がんを効率的に攻撃するよう活性化させてから再び体内に戻す免疫細胞治療を行っています。当院では患者さんの免疫細胞やがん細胞の状態を綿密に検査し、一人ひとりに適したオーダーメード医療を採用しているため、より効率的な再発防止を期待できます。
がん再発に不安がある方や、再発のリスクを軽減したい方は、ぜひ瀬田クリニック東京にご相談ください。
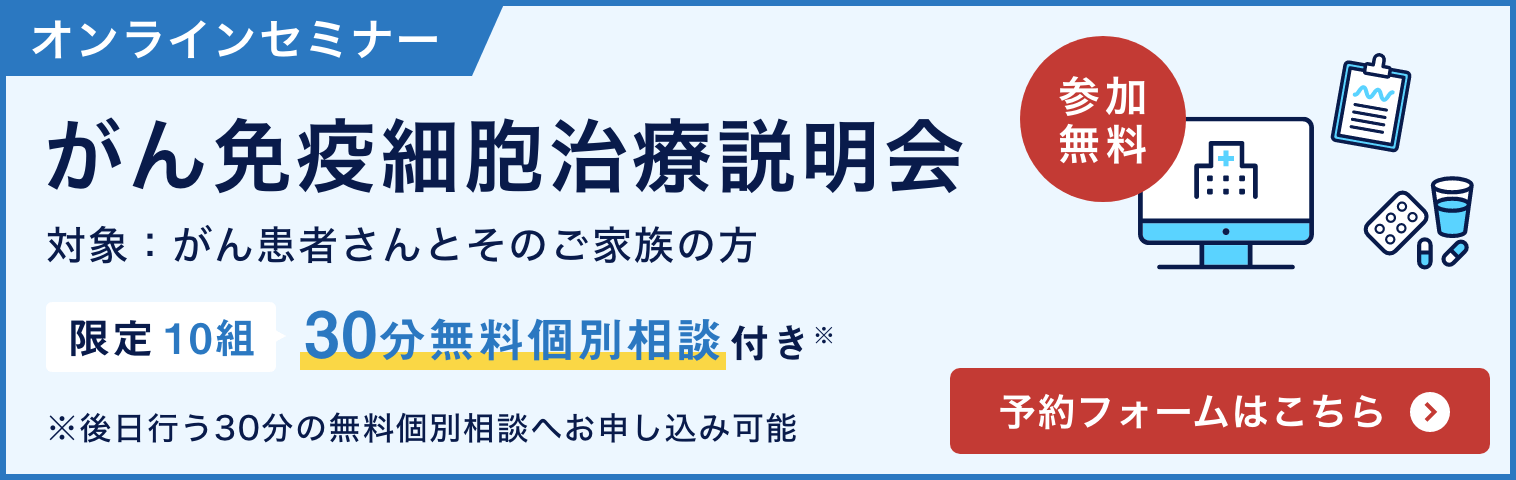
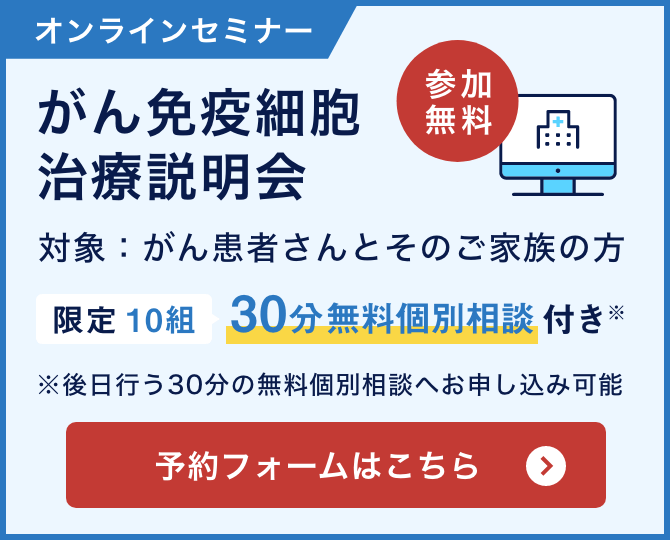
無料

- 資料請求・お問合せ
 当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
詳しくはお電話やフォームからお申込みください。
- メールフォームはこちら
資料請求
関連性の高いコラム記事
-

ストレスは悪性リンパ腫の原因になる?リスク要因や免疫との関係も含めて解説
2025.11.14瀬田クリニック東京
-
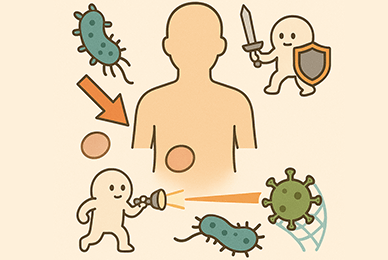
免疫力の高い人の特徴は?免疫力アップの方法を解説
2025.06.20瀬田クリニック東京
-
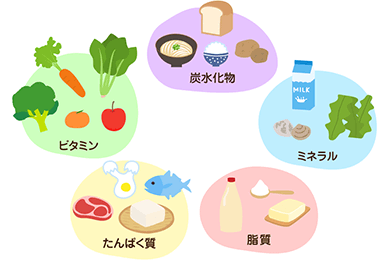
がん細胞が嫌う食べ物・生活習慣とは?がんに対応するための具体的なポイントを解説
2025.06.06瀬田クリニック東京
-

がん治療後、仕事に復帰するために必要な手続きや準備を分かりやすく解説
2025.04.11瀬田クリニック東京
-

がん再発への不安が消えない場合はどうする?不安から生じる症状や不安
2025.03.21瀬田クリニック東京
-

親ががんになって仕事が手につかないときはどうする?親のがんとの向き合い方と自身のケアの仕方を解説
2025.03.07瀬田クリニック東京
-
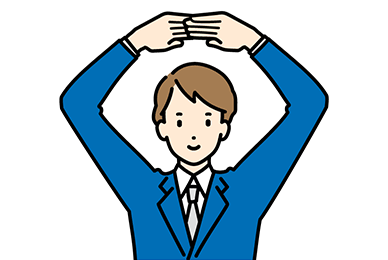
がん治療中でも働ける仕事とは?仕事を続けるメリット・デメリットや働きやすい環境を紹介
2025.02.28瀬田クリニック東京
-

がんになっても運動は重要?がん予防と運動の関係や効果、具体的な方法を解説
2025.01.31瀬田クリニック東京
-
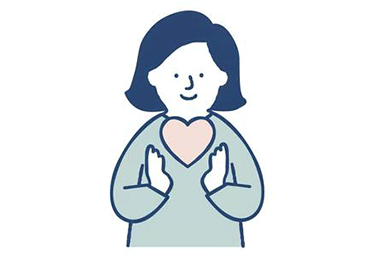
がん患者さんに多い精神症状とは?がんと診断されたときの心の変化やストレスへの対処法を紹介
2025.01.17瀬田クリニック東京
-

がんを怖いと感じる理由とは?がんに対する恐怖心や不安との向き合い方
2024.12.20瀬田クリニック東京
-

がん治療中の食事とは?副作用が出た時の食事や食事療法の注意点を解説
2024.11.1瀬田クリニック東京
 CHINESE
CHINESE
 無料説明会
無料説明会 資料請求
資料請求