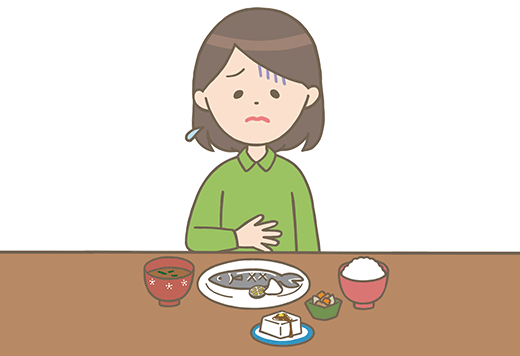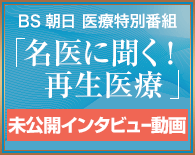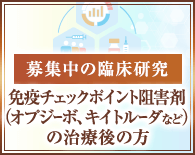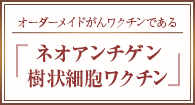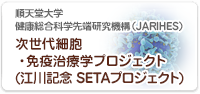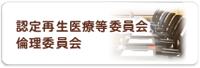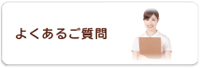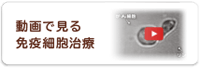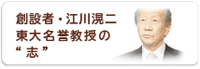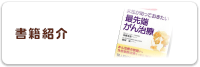がん治療中に「お腹が空かない」と感じる患者さんは少なくありません。食欲不振はがんの症状の一つですが、治療の副作用や心理的な負担などのさまざまな要因が複雑に絡み合っています。
本記事では、がんによる食欲不振の原因やその対策を解説します。患者さんが少しでも生活の質を保ちながら治療に専念できるよう、治療法から食事の工夫も併せて説明します。
無料

- 資料請求・お問合せ
 当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
詳しくはお電話やフォームからお申込みください。
- メールフォームはこちら
資料請求
がんによる食欲不振の原因とは?
がんによる食欲不振は、がん自体が引き起こす影響だけではなく、治療に伴う副作用や心理的な要因などが関わっています。具体的な原因を知ることで、適切な対策を見つける手がかりにもなるため、以下で詳しく見ていきましょう。
- ●がんが引き起こす身体的な要因
- ●治療の副作用が引き起こす影響
- ●治療の不安から来る心理的な要因
がんが引き起こす身体的な要因
食欲不振の原因として第一に考えられるのは、がんが引き起こす身体的な要因です(※1)。
多くのがんの症状には、胃炎や吐き気、下痢などの消化器系に影響を及ぼすものが含まれます。消化器系の症状だけでなく、息苦しさや痛み、飲み込みにくさなどの他の身体的な不快感も原因となるケースがあります。例えば、胃がんの主な症状は胸やけや胃の痛み、吐き気、食欲不振などです(※2)。
また全てのがんに当てはまる要因として、がん悪液質が挙げられます。がん悪液質とは、がん細胞がエネルギーを過剰に消費することで体全体の代謝バランスが崩れ、筋肉や脂肪が急速に失われる状態のことです。
この状態が起こるメカニズムは、がん細胞が作る物質「サイトカイン」が大きく関わっています。サイトカインは、脳の食欲に直結する神経の力を抑制するといわれており、結果として食欲不振が強く出てしまう可能性があります。
※1参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「食欲がない・食欲不振 もっと詳しく~がんの治療を始める人に、始めた人に~」.
https://ganjoho.jp/public/support/condition/anorexia/ld01.html ,(参照2024-12-218).
※2参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「胃がんについて」.
https://ganjoho.jp/public/cancer/stomach/about.html ,(参照2024-12-21).
治療の副作用が引き起こす影響
治療の副作用も食欲不振の原因の一つです。特に抗がん剤治療や放射線治療では、吐き気や嘔吐、口内炎、下痢といった不調がよく見られます。
抗がん剤治療では、体内のがん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を及ぼすため、さまざまな副作用が現れます。がんの位置によっては、消化器官の粘膜がダメージを受けて食欲不振を来すこともあるのです。消化器官は、食べ物が体内に入る際に中枢神経を刺激し、食欲を増進させる役割も担っています。この仕組みが正常に機能しないと、脳に「食べたい」「お腹が空いた」という信号が伝わりにくくなり、食欲の低下が進むことがあります。
また、放射線治療でも照射部位によっては食欲不振を引き起こす可能性が高いです。口やのど周辺のがんを照射する場合、口内炎ができて食事が取りづらくなります。さらに食道がんの場合は、放射線が食道の粘膜に炎症を引き起こし、飲み込む際に痛みや違和感を覚えることがあります。
治療の不安から来る心理的な要因
がん治療に伴う不安やストレスは、食欲不振を引き起こす大きな心理的要因となります(※)。治療そのものに対する恐怖や不安、治療効果への期待と不安が入り混じる感情、さらには病気が日常生活に与える影響についての心配など、患者さんが抱える心の負担は計り知れません。
がんと告げられた際は、病気への恐怖や将来への不安が一気に押し寄せることもあるでしょう。「これからどうなるのか」「治療に耐えられるのか」といった漠然とした不安だけでなく、家族や仕事、生活全般への影響を心配する方も多いです。
また治療の過程で体調が悪化したり、副作用が続いたりすると「何を食べても意味がないのでは」「食べても気持ち悪くなるだけでは」といった否定的な思考に陥ることもあります。心理的負担が大きくなると、不安障害やうつ病、気分の落ち込みが起こる可能性があります。
※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「がんと心」.
https://ganjoho.jp/public/support/mental_care/mc01.html ,(参照2024-12-21).
食欲不振への具体的な対策
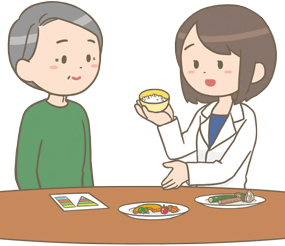
食欲不振の具体的な対策は、以下の通りです。
- ●食事の取り方を工夫する
- ●快適に食事が取れる環境を整える
- ●医療者へ食欲不振を相談する
食事の取り方を工夫する
食欲不振が起こったときは、食事の取り方を工夫してみましょう。具体的には以下の通りです。
- ●消化が良く、飲み込みやすい食べ物を選ぶ
- ●味付けを変えてみる
- ●少量を小まめに摂取する
- ●臭みを消してみる
- ●手軽に食べられるものを用意しておく
- ●栄養素が豊富に含まれている食べ物を食べる
消化が良く、飲み込みやすい食べ物を選ぶ
体に負担をかけず、消化が良く飲み込みやすい食べ物を選んでみましょう。軟らかくのどごしが良い食感の食品を取り入れると良いでしょう(※1)。
消化の良い食品と避けた方がよい食品は、以下の通りです(※2)。
| 消化の良い食品 | 避けた方がよい食品 | |
|---|---|---|
| 主食 |
|
|
| 主菜 |
|
|
| 副菜 |
|
|
| 果物 |
|
|
| その他 |
|
|
これらの食品リストを参考に、自分の体調や好みに合った食べ物を取り入れてみてください。ただし、適切な食事内容は患者さんごとに異なります。食事については主治医や管理栄養士と相談しながら決めていきましょう。
※1参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「食欲がない・食欲不振 もっと詳しく~がんの治療を始める人に、始めた人に~」.
https://ganjoho.jp/public/support/condition/anorexia/ld01.html ,(参照2024-12-21).
※2参考:国立がん研究センター.「消化の良いもの・悪いもの」.
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/CHEER/advice/070/002_syoukakijyutugo.pdf ,(参照2024-12-21).
味付けを変えてみる
普段と異なる味付けを試してみることで食事が刺激されることがあります。がん治療中は味覚や嗅覚が変化することがあり、以前好きだった味が苦手になるケースも少なくありません。同じ食材や料理でも味付けを工夫するだけで、新鮮な気持ちで食事を楽しめるようになる可能性があります。
例えば、味をあまり感じなくなった場合は、レモンやゆず、スパイスや香辛料などで料理にアクセントを加えてみると良いでしょう。金属の味がして食欲が湧かないときは、塩気を控えつつもみそやごま、マヨネーズなどで風味を加えてみるのも一つの方法です。塩気を感じる場合は、だしを追加したり、洋食にしてみたりと工夫を加えてみましょう(※1)。なお、口内炎があるときは刺激のある食べ物で痛みを感じる場合があるため、注意してください。
※参考:国立がん研究センター.「味覚やにおいの変化 もっと詳しく」.
https://ganjoho.jp/public/support/condition/taste_or_smell/ld01.html ,(参照2024-12-21).
少量を小まめに摂取する
食欲が出ないときは、一度に食べようとせず少量を小まめに分けて摂取しましょう。食欲がないときは1日3回の食事にこだわらず、食べたいときに少しずつ食べるのが大切です。
がん治療は必要以上にエネルギーを使うため、食事で体力を維持しなければなりません。しかし、食事の回数にとらわれ過ぎてしまうと「しっかり食べなければ」とプレッシャーを感じてしまい、かえって食事が負担になってしまう場合があります。
そのため、食事は自分のペースに合わせて無理せず取りましょう。ただし、がんとは異なる病気が併発している場合は、また別な食事管理が必要となる可能性があるため、主治医や管理栄養士に相談しましょう。
臭みを消してみる
料理の臭みを消してみるのも方法の一つです。特に魚や肉など、調理中の匂いが気になる場合、工夫次第で食べやすさが大きく変わります。臭みが強いと感じる食材には、いつもより念入りに下処理をしたり調味料を変えたりしてみましょう。
例えば、魚の臭みを和らげるには、調理前に塩を振ってお酒に漬けるのがおすすめです。また肉の臭みは、お酒や牛乳に漬けると抑えられます。さらに全体的にショウガやシソを使ってみたり、加熱でなく湯通しをしてみたりするのも効果的です。
なお、出来立ての料理で匂いを強く感じる場合は、少し冷ましてから食べると良いでしょう(※)。また、にんにくやレバー、ニラなどの元々の匂いが強い食材を避ける方法もあります。
※参考:国立がんセンター東病院栄養管理室.「抗がん剤治療中の簡単・お助けレシピ」.
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/division/nutrition_management/info/seminar/recipe/recipe017.pdf ,(参照2024-12-21).
手軽に食べられるものを用意しておく
手軽に食べられるものをあらかじめ用意しておくと便利です。簡単な食べ物は調理の手間や負担が軽減され、気軽に栄養を補給できます。
例えば、パンやおにぎり、ゼリー、ゆで卵など、そのまま食べられる食品をストックしておくと「食べたい」と思ったときにすぐに食事が取れます。ただし、無理に食べる必要はありません。体調に合わせて食べられそうなものを準備しておきましょう。
栄養素が豊富に含まれている食べ物を食べる
食欲がないときは、少量で効率良く栄養を摂取できる食品を選ぶのがおすすめです。がん患者さんが少しでも前向きに治療に向き合うために大事なのは、体重を維持して痩せないようにすることです。体重が減少すると、体力が低下して治療に必要なエネルギーを確保できなくなる可能性があります。
食べられそうなときは、できるだけ栄養バランスを意識して食事を取るのが大切です。たんぱく質や炭水化物、脂質に加え、ビタミンやミネラルなどの栄養素をバランス良く取り入れることで、体力を維持しやすくなります。
中でも大切なのは、体のエネルギー源になるたんぱく質です。たんぱく質が不足すると、免疫機能が低下して体重減少の原因となります。特にBCAA(分岐鎖アミノ酸)を含む以下の食材を積極的に取りましょう。
- ●牛肉
- ●鶏肉
- ●カツオ
- ●マグロ
- ●卵
- ●チーズ
BCAAには、筋肉の維持や修復、体力回復をサポートする働きがあります。栄養バランスの取れた食事を心掛けつつ、たんぱく質を積極的に摂取しましょう。
快適に食事が取れる環境を整える
食欲不振の改善には、快適な食事環境の整備が大切です。食事中の姿勢に気を付けたり、周囲の人と協力し合いながら食べたいものを見つけたり、少しずつ食事環境を整えていきましょう。
座って食べるのが難しい場合は、上体を45~60度起こし、顎を引いて食べてみましょう。この姿勢を取ると消化を助けるだけでなく、誤嚥(食べ物や飲み物が気道に入ること)のリスクを軽減する効果もあります(※)。
なお、患者さんのサポートに回る方は、無理に食事を促さず、ご本人のペースに寄り添いましょう。「食べてほしい」「早く病気を治してほしい」と思う気持ちは自然に出てくるものです。しかし、その思いが時として患者さんにプレッシャーを与える可能性もあります。患者さんの気持ちに寄り添いながら、少しずつ快適な食事環境を整えていきましょう。
※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「がんと食事」.
https://ganjoho.jp/public/support/dietarylife/index.html ,(参照2024-12-21).
医療者へ食欲不振の旨を相談する
食欲不振が続く場合や日常生活に影響を来している場合は、主治医や看護師に相談しましょう。
患者さんによって治療の進み具合や体調の変化には個人差があるため、食欲不振が出る時期や程度も異なります。例えば、手術療法では特に手術直後に食欲低下を来すことが多いです。また薬物療法では、治療後1週間程度で副作用として吐き気や味覚の変化が現れる場合があります。放射線治療では、治療開始から約10日後に食欲不振が現れる可能性があり、その後も数カ月にわたって症状が続くケースも考えられます(※)。
このように、治療方法や時期によって症状の出方や回復のタイミングが異なるため、食欲不振が続く場合は早めに医師や看護師に相談し、適切な対策を講じましょう。
※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター
「食欲がない・食欲不振 もっと詳しく~がんの治療を始める人に、始めた人に~」.
https://ganjoho.jp/public/support/condition/anorexia/ld01.html ,(参照2024-12-21).
がんの治療法は主に4つある
がんの治療法は、主に以下の4つです。どの治療で進めていくのかは、患者さんの体調やがんの進行度、希望によって異なります。
- ●手術療法
- ●放射線治療
- ●薬物療法
- ●免疫療法
手術療法:がんを摘出手術で直接取り除く
手術療法は、がんやその周辺の臓器を直接取り除く方法です。がん細胞は、進行すると他の部位や周辺の組織に転移する場合があるため、周辺の組織を含めて広範囲に切除するのが一般的です。
基本的には、がんの部位や進行状況に合わせて以下の方法で治療を進めていきます(※)。
- ●開腹手術
- ●開胸手術
- ●腹腔鏡下手術
- ●内視鏡治療
手術療法は直接がんを取り除く方法のため、根治を目指せる可能性が高い点がメリットです。一方、手術の規模や部位によっては体への負担が大きくかかるため、早期発見がんであれば内視鏡治療や腹腔鏡下手術などを用いる場合もあります。
※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「手術(外科治療)」.
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/operation/index.html ,(参照2024-12-21).
放射線治療:がん細胞に放射線を当てて攻撃する
放射線治療は、放射線をがん細胞に当てて攻撃することで完治を目指す方法です。放射線はがん細胞のDNAを死滅させ、増殖や分裂を妨げることで効果を発揮します。
他の治療法より体への負担が少なく、臓器の機能を維持したまま治療を進められるのが特徴です。放射線治療は、リニアックと呼ばれる装置を使って、体の外側から放射線を当てていきます。通院で治療を進められるケースがほとんどで、生活の質を維持しながら完治や症状緩和を目指せる点がメリットです(※)。
※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「放射線治療」.
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/radiotherapy/index.html,(参照2024-12-21).
薬物療法:特定の薬を使って治療を進める
薬物療法とは、特定の薬を使って治療を進める方法です。単独で治療を進めていくケースもあれば、他の治療法と併用で進めていくケースもあります。
主に使う薬は、以下の3つです(※)。
- ●細胞障害性抗がん薬:
がん細胞の増殖を抑え、細胞分裂を阻害する - ●内分泌療法薬:
ホルモンの分泌や作用を抑制し、がん細胞の成長を妨げる - ●分子標的薬:
がん増殖のもととなる特定の遺伝子やたんぱく質を狙って攻撃する
薬物療法は、患者さんの体調に合わせて入院もしくは通院で治療を進めていきます。治療中は副作用を軽減し、体力を維持するためのサポートが必要となる場合があります。
※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「薬物療法」.
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/drug_therapy/index.html ,(参照2024-12-21).
免疫療法:患者さんの免疫機能を生かして治療を進める
免疫療法とは、患者さんが元々持っている免疫機能を生かして治療を進めていく方法です。免疫とは、体の中に入った異物や異常な細胞を排除しようとするシステムです。
免疫細胞の中にあるT細胞は、がん細胞を攻撃する役割を果たしていますが、T細胞ががんによってダメージを受けると攻撃力が弱まります。免疫療法では、T細胞の攻撃力を維持しながら再び活性化させることで、がん細胞に対する免疫の働きを強化します(※)。
他の治療とも併用でき、全身への負担も比較的少ないため、普段通りの生活を送りながら治療を進められるのがメリットです。
※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「免疫療法」.
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/immunotherapy/index.html ,(参照2024-12-21).
がんによる食欲不振には、身体的な要素や副作用、心理的な要素が関わっている
がんによる食欲不振は、がんの症状の一つです。また治療の副作用も大きな要因であり、抗がん剤や放射線治療による吐き気や味覚の変化、口内炎などが食事を取る妨げになるケースもあります。
また、心理的な要素も見逃せません。治療に対する不安や生活の変化などがストレスとなり、食欲が湧かない可能性もあります。食事の取り方に工夫を取り入れつつ、周囲の方のサポートを受けながら、自分に合った食事を考えていきましょう。
瀬田クリニック東京では、患者さん一人ひとりに合わせた免疫細胞治療を行っています。当院ではがん細胞に関係する遺伝子を解析し、それに基づいた個別化がん免疫療法を提案しています。「がん治療で副作用の少ない治療をしたい」とお考えの方は、ぜひ瀬田クリニック東京にご相談ください。
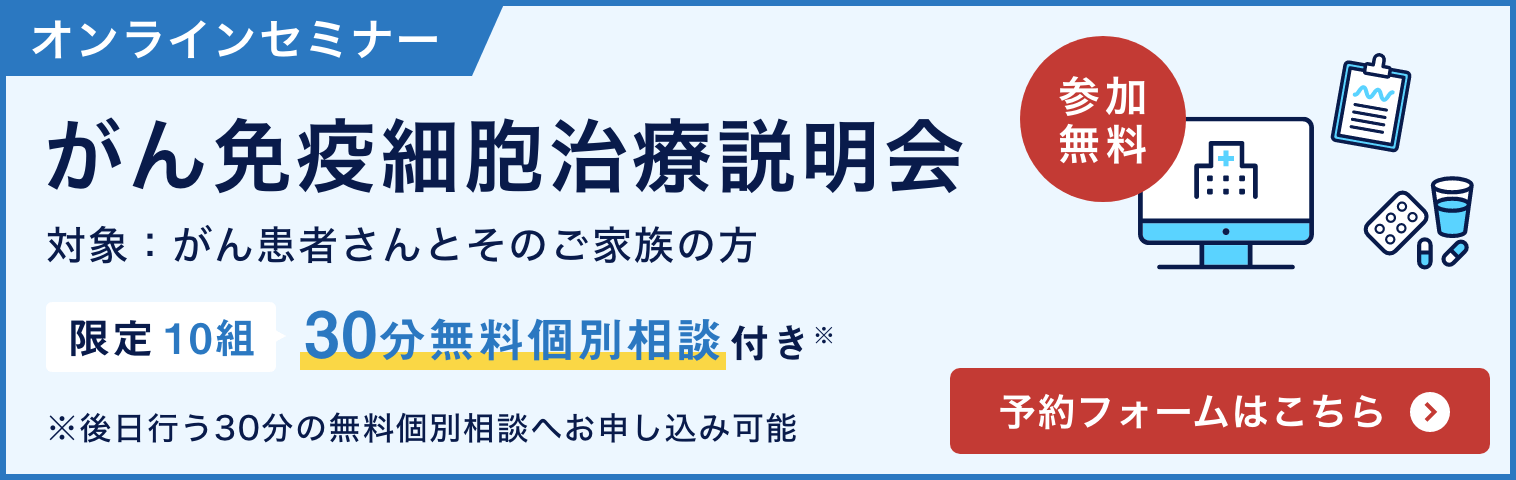
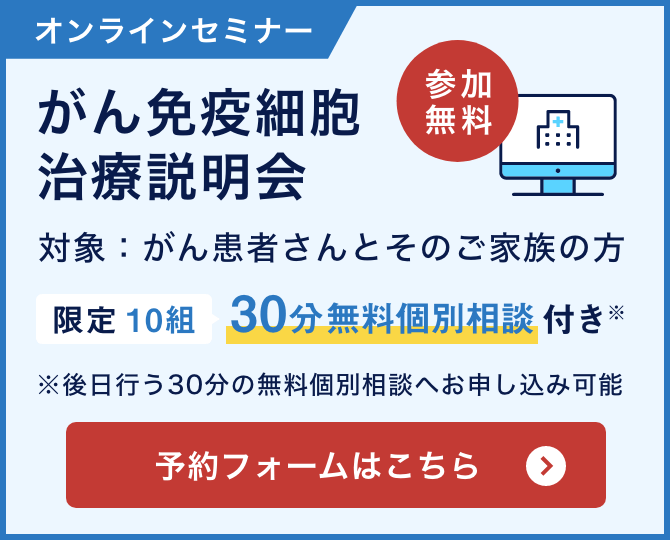
無料

- 資料請求・お問合せ
 当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。
詳しくはお電話やフォームからお申込みください。
- メールフォームはこちら
資料請求
 CHINESE
CHINESE